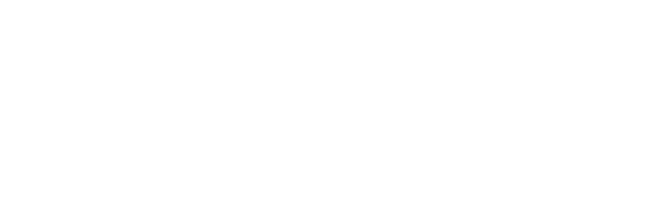ごめんください。Gallup 認定ストレングスコーチのコスギです。
今回は、“コーチング” を提供している方なら知っておきたい最新情報をまとめました。
ICF(International Coaching Federation/国際コーチング連盟)のコア・コンピテンシー(以下、ICFコアコン)は、コーチングを倫理的かつ効果的に行うための行動基準であり、クライアントとの共創を支える土台であり、学習・振り返り・評価まで一貫して使える共通言語です。
コーチング資格の種類に関わらず、間違ったコーチングをしない(コーチングではないことを “コーチング” として提供しない)ためにも、このICFコアコンは心身に叩き込んでおくべきものだと、個人的には思う所存です。自戒も込めて……コーチングと名のつくものを提供するのなら、ICFコアコンでトレーニングするのが王道であり近道ですわ。
なお、ICFの倫理規定やコア・コンピテンシーを学ぶなら、コアコンみんなの学び場がオススメです。マスタークラスのコーチがグループ学習をサポートしてくれるので間違いありません。
2025年版 ICF コア・コンピテンシーの主な変更点
ICFは5〜7年ごとに大規模な職務分析を行って、コーチングの現場の声を反映させています。今回の2025年版も、世界中のコーチたちの声を反映したものですね。この変化を追うことで、今、何が起きていて何が求められているのかがわかります。今回は、ざっくり4点。
5つの新しいサブ・コンピテンシーの追加
まず、コンピテンシー 2「コーチングマインドを体現している」の定義が更新(追加)されたことに関わるのか、2つ追加されています。
2.09. Nurtures openness and curiosity in oneself, the client, and the coaching process.
(自分自身、クライアント、そしてコーチングプロセスにおいて、開放性と好奇心を育んでいる)
2.10. Remains aware of the influence of one’s thoughts and behaviors on the client and others
(常に自身の思考や行動がクライアントや周囲の人々に与える影響を認識している)
curiosity(好奇心)はコンピテンシー 5「今ここに在り続ける」にもありますが、コンピテンシー 2 は「コーチングマインドの体現」なので、コーチのあり方として開放的で好奇心を持つという姿勢が、環境として影響を与えることになると明言されたのかな、とも。ICFコアコンの他の項目をみると、「開放的」というのは「囚われない」と同義のような。
つまり、個人の特性ではなく「コーチとして好奇心というスキルを育てて、自分をメタ認識できるようにしておきなさいね」という話ですかね。
3.12. Revisits the coaching agreement when necessary to ensure the coaching approach is meeting the client’s needs
(必要に応じてコーチングの契約内容を見直し、そのアプローチがクライアントのニーズに確実に応えられている)
コンピテンシー 3 は「合意の確立と維持」です。合意は固定的なものではなく、クライアントのニーズに合わせて見直すものであると明言された印象です。つまり、「予定通り進めるセッション」から「必要な進め方に合わせ直すセッション」と、柔軟性が増しましたね。
これは先述の 2.09 と 2.10 に強く関係し、クライアントのニーズをしっかりと捉えないと柔軟に対応できないということでもありそうです。
5.03. Remains aware of what is emerging for self and client in the present moment
(今ここにおいて、常に自分自身とクライアントにとって何が起きているのかを意識し続けている)
コンピテンシー 5 は「今ここに在り続ける」です。先述の 2.09 の curiosity(好奇心)は 5.02 にあり、その流れで 5.03 に差し込まれたことに注目したい。ただ好奇心を持つだけでなく、好奇心を持つことでコーチとクライアントの間に何が起こっているのかを認識している必要があるよ、と。
自分で訳していてなんですが、emerging[新しく現れつつある・発展途上の]というワードは(ICFコアコン内で)初出なので、「何が起きているのか」より「どんな兆しがあるのか」と表現したほうがわかりやすいかもしれません。
8.07. Partners with the client to integrate learning and sustain progress throughout the coaching engagement
(クライアントとパートナー関係を築き、コーチング契約を通じて学習を統合し、進歩を持続している)
コンピテンシー 8 は「クライアントの成長を促進する」です。sustain progress[進歩を持続する]という言葉にもあるように、単一セッション内だけでなく、コーチング契約全体の期間を通じて学習が定着し、進歩が持続する点が強調された印象です。点ではなく線形で関わり、長期的に影響するコミットメントを重視したような。
11の既存のサブ・コンピテンシーの改訂
まずは、コンピテンシー 2「コーチングマインドを体現している」から4件。
2.02. Engages in ongoing learning and development as a coach
(コーチとして継続的な学習と能力開発を行なっている)
2.02. Engages in ongoing learning and development as a coach, including remaining aware of current coaching best practices and use of technology
(コーチとして継続的な学習と能力開発を行なっており、常に最新のコーチング手法やテクノロジー活用の動向を把握している)
AIを始めとしたテクノロジーの進化に対応し、コーチが最新の手法やツールを認識し続けることの必要性が追加されました。ICFはAIコーチングの基準も示しているので、それもふまえての改訂と考えられます。
2.04. Remains aware of and open to the influence of context and culture on self and others
(常に自身と他者の状況や文化の影響を意識しつつも、それに捉われないでいる)
2.04. Remains aware of and open to the influence of biases, context and culture on self and others
(常に自身と他者に対するバイアス、状況や文化の影響を意識しつつも、それに捉われないでいる)
これは追加された 2.10 に通じるものがありますね。コーチが自身のバイアス(偏見、仮定、解釈から生じる知覚の違い)を認識し、対応する意識を高めることが求められます。メタ認識、大事。
2.06. Develops and maintains the ability to regulate one’s emotions
(感情を整える能力を開発し、維持している)
2.06. Develops and maintains the ability to manage one’s emotions
(感情を整える能力を開発し、維持している)
あえて和訳はそのまま。以前の「感情を規制する (regulate)」というニュアンスから「感情を管理する (manage)」に変更され、より積極的で意図的な感情への対処が求められるようになりました。ここでもメタ認識の重要性が伺えますね。
2.07. Mentally and emotionally prepares for sessions
(セッションに備え、精神的及び感情的な準備をしている)
2.07. Maintains emotional, physical, and mental well-being in preparation for, throughout, and following each session.
(各セッションの前後および実施中を通じて、感情的、身体的、精神的な健全性を維持している)
これまでは準備にフォーカスされていたのが、セッション全体を通じてコーチ自身のウェルビーイングが重要であることが強調され、まるっと変わりました。追加された 2.10 や 8.07 に通じるような、コーチの状態が影響を与えるからこそ、一貫性が大事って話のように思えます。ウェルビーイングをどう訳すかなあ……
次は、コンピテンシー 3「合意の確立と維持」から3件。
3.01. Explains what coaching is and is not and describes the process to the client and relevant stakeholders
(コーチングとは何で、何でないのかを説明し、クライアントと関連する利害関係者にプロセスを説明している)
3.01. Describes one’s coaching philosophy and clearly defines what coaching is and is not for potential clients and stakeholders
(自身のコーチング哲学を説明し、コーチングとは何で、何でないのかを潜在的なクライアントや利害関係者に明確に定義している)
「自分のコーチング哲学を語る」という、なかなかオモシロイ改訂です。メンターコーチングでもスーパーバイザーでも、自分らしいコーチのあり方を無視するものではないので、スーパーバイザーが明言されたことに関わっているのかもしれません。「私にとってコーチングとはこういうものです」と明言できることが、コーチ自身の軸にもなりそうですね。
3.02. Reaches agreement about what is and is not appropriate in the relationship, what is and is not being offered, and the responsibilities of the client and relevant stakeholders
(コーチとクライアントとの関係性の中で、何が適切で何が適切でないか、何が提供され何が提供されないか、およびクライアントと関連する利害関係者の責任について合意に達している)
3.02. Reaches agreement about what is and is not appropriate in the relationship, what is and is not being offered, and the responsibilities of the client and relevant stakeholders, including commitment to working toward coaching goals
(コーチとクライアントとの関係性の中で、何が適切で何が適切でないか、何が提供され何が提供されないか、およびクライアントと関連する利害関係者の責任、さらにコーチングの目標に向けて取り組むことへのコミットメントについて合意に達している)
単に境界線と役割を明確にするだけでなく、合意そのものを “目標志向の共同契約” にするねらいがありそうです。つまり、クライアントにも目標を持って主体的にコミットしていく当事者であることの合意をすべきという話ですね。コーチとの関係性によって得られるものに、コーチングの目標が明記されたことは大きいかもしれません。
3.11. Partners with the client to end the coaching relationship in a way that honors the experience
(価値ある経験としてコーチング関係を終了するために、クライアントと協力し合っている)
3.11. Partners with the client to close the coaching relationship in a way that respects the client and the coaching experience
(クライアントとコーチング経験を尊重してコーチング関係に区切りをつけるために、クライアントと協力し合っている)
「end」から「close」に変わったのが興味深いですね。「end」は完全に終わりの印象ですが、「close」は連続性の中にある終わりの印象です。ここから、和訳も「区切り」としました。後半も、「セッションを振り返って終わり」といった事務的な対応ではなく、クライアントが得た学びや変化を持ち帰って次につながるような対応に変わった感じがします。
4と5はそのままで、次はコンピテンシー 6「積極的傾聴」から2件です。同じような改訂なのでまとめて。
6.02. Reflects or summarizes what the client communicated to ensure clarity and understanding
(クライアントが伝えた内容を反復または要約することで、明確さと理解度を高めている)
6.02. Reflects or summarizes what the client is communicating to ensure clarity and understanding
(クライアントが伝えている内容を反復または要約することで、明確さと理解度を高めている)
6.05. Integrates the client’s words, tone of voice and body language to determine the full meaning of what is being communicated
(クライアントの言葉、声のトーン、ボディランゲージからの情報を統合し、伝えられていること全体の意味を把握している)
6.05. Integrates the client’s words, tone of voice and body language to determine the full meaning of what the client is communicating
(クライアントの言葉、声のトーン、ボディランゲージからの情報を統合し、クライアントが伝えていることの全体の意味を把握している)
どちらも、過去形が現在進行系になりました。「今ここ」に集中して、「クライアントが伝えていること」に能動的に耳を傾ける姿勢が強調されている印象です。こういう微妙な調整、大好きなんですよねえ。
次は、コンピテンシー 7「気づきを引き起こす」から1件。
7.11. Shares observations, insights and feelings, without attachment, that have the potential to create new learning for the client
(クライアントが新しい学びを生み出す可能性を持てるように、観察、洞察、感情を、それに固執することなく共有している)
7.11. Shares observations, knowledge, and feelings, without attachment, that have the potential to create new insights for the client
(クライアントが新しい洞察を生み出す可能性を持てるように、観察、知識、感情を、それに固執することなく共有している)
気づきを引き起こす目的は「学習」よりも「洞察(≒深く考察して新しい視点を得ること)」で、そのためにコーチが知識を共有することも厭わないというニュアンスの変化ですかね。あくまで、洞察を生み出すのはクライアントだと。ここは、ティーチングとコーチングとの違いに関わりそうです。目的が違う。
最後に、コンピテンシー 8「クライアントの成長を促進する」から1件。8.07 に新しく追加されたので、後ろにズレます。
8.07 Celebrates the client’s progress and successes
(クライアントの成長と成功を祝福している)
8.08. Acknowledges the client’s progress and successes
(クライアントの成長と成功を承認している)
ちょっと事務的になった印象ですね。「一緒に盛り上がること」が目的ではなく、クライアントが自分の成長や成功を実感できるよう、客観的に承認する役割だと明言されました。文化や関係性によっては、過度に感情的・主観的に受け取られるリスクがあったようです。個人的に、「祝福」という文言は好きだったのですが、倫理規定にも関わる部分なので、なるほど感。
1つの主要コンピテンシーの定義を更新
2. Embodies a Coaching Mindset(コーチングマインドを体現している)の定義が変更されました。前半が追加されていますね。
2019年版
Definition: Develops and maintains a mindset that is open, curious, flexible and client-centered
定義:開放的で、好奇心を持ち、柔軟性があり、クライアントを中心に据えた、思考態度を開発し、維持している
2025年版
Definition: Engages in ongoing personal and professional learning and development as a coach. Works with coaching supervisors or mentor coaches as needed. Develops and maintains a mindset that is open, curious, flexible and client-centered.
定義:コーチとして継続的に自己および専門的能力の開発に取り組む。必要に応じてコーチング・スーパーバイザーまたはメンターコーチと協力する。開放的で、好奇心を持ち、柔軟性があり、クライアントを中心に据えた、思考態度を開発し、維持している。
コーチが自身の成長を継続的に追求することの重要性が強調されました。コーチングの専門性向上と倫理的な実践が今になって強調されているのは、コーチングがまた流行語になっている印象がありますね……AIも出てきてますしね。
ちなみに、「コーチング・スーパーバイザー」と「メンターコーチ」は、どちらも “コーチ向けのコーチ” ですが、(ざっくりと)以下のような違いがあります。併用するとメキメキ伸びます。
- コーチング・スーパーバイザー
-
コーチングのスキル以上に、コーチとしての在り方を整えるためのものです。倫理的成熟を目指します。
- メンターコーチ
-
コーチングスキルそのものへの具体的なフィードバックを行うものです。資格取得に直結しやすいですね。
用語集の新設(50件)
倫理規定にも一部の用語がありましたが、ICFコアコンにも用語が50件追加されました。これはICFジャパンの和訳を待ちたいところですが、学習がてら挙げてみたいとは思います。そのうち……
まとめ:正解はないけれど不正解はあると思う
コーチには国家資格がないように、正解がありません。コーチングそのものの定義も、割とtバラバラなんです。コーチと名乗ればコーチです。そんな業界なので、敬遠されるのも無理はありません。だからこそ、ICFが先頭に立って国際基準をつくっているんだろうなと。
私自身、基本のコーチングを学ぶ前にクリフトンストレングス(ストレングスファインダー)に入ったので、「ストレングスコーチング」が「ストレングスティーチング」や「ストレングスコンサルティング」になっていた時期が短くありません。ICFの資格はともかく、せめてコアコンを学んでおけばよかったなと思うものの、周りを見渡せば、同じようなストレングスコーチがいて、同じように迷っているストレングスコーチたちがいることを実感しています。
正直、ICFの倫理規定やコアコンって、修行僧みたいじゃないですか。聖人かってくらい。でも、それがコーチという存在なんですよね。
コーチは相手の気づきの瞬間に立ち会える、キラキラした仕事に見えるかもしれません。しかし実際は、その環境を整えるコーチ自身が「自我を持ちながらも自我をコントロールする」という離れワザを要求されます。正直、面倒くさいというか、よっぽど自我を持たないAIのほうが効果的なコーチングを提供できるんじゃないかとも思います。
よく、コーチとクライアントは「相性」と言われますが、ICFコアコンを学ぶと、単なる「相性」では片付けられない、クライアントから選ばれ続けるためのコーチとしてのあり方の重要性を痛感します。
恋愛や婚活でもありますよね。自分としては感触が良いと思った相手が、実は忖度してくれていたこととか。そういった “クライアント力” が高いクライアントなら、どんな未熟なコーチからも貪欲に成長しますが、それで継続的なパートナー関係になれるかといえば、そんなこともないでしょう。
コーチングは、入口あって出口なしと言われる道なので、コーチが自分のコーチングに満足してしまったら、それはもうコーチではないのでしょう。だから、安易にコーチになろうと思わないほうがいいし、コーチを目指しても「自分には無理だな」と別のキャリアを選ぶことも大事だと思います。AIに代替されかねませんし。
それでも、AIにはできない、人間だからこそできるコーチングを追求していきたいのであれば、ICFの倫理規定やコアコンが照らしてくれる道があります。日本の国家資格ではないけれど、世界の国際基準なので。
あとは、「自身のコーチング哲学」をどう語るか。私は今のところ、「コーチは人生のサードパートナーである」としていますが、コーチングそのものはどうかな。もう少し考えてみます。
さてさて、私は得た知識をアウトプットしながら独学したほうが吸収しやすいため、今後もICFの倫理規定やコアコンそれぞれについて記事を書いていきますが、ほとんどの方はグループ学習のほうが効率が良いので、マスタークラスの資格保持者が運営している「コアコンみんなの学び場」を(もう一度)オススメしておきます。
また、ICFジャパンが主催しているイベントも学べる機会としてオススメなので、こちらもどうぞ。