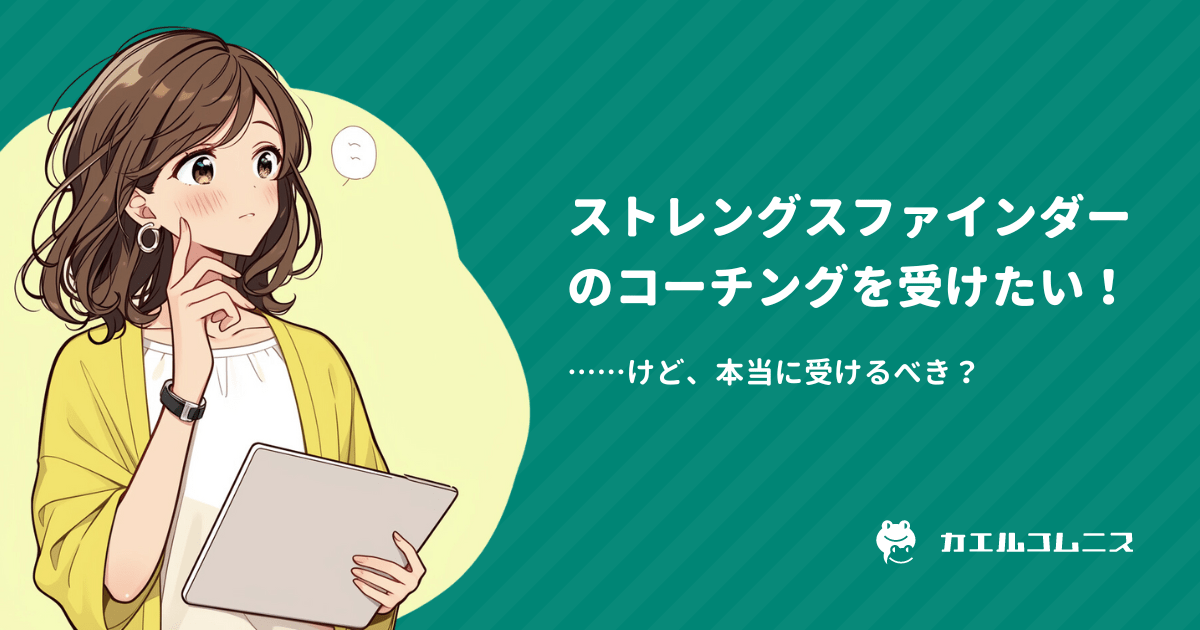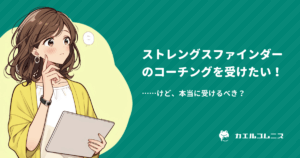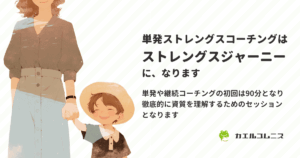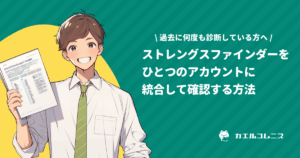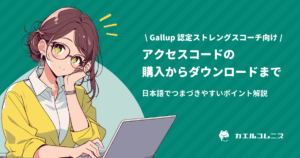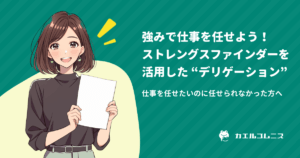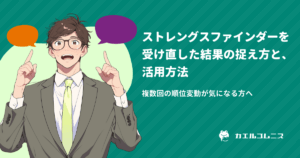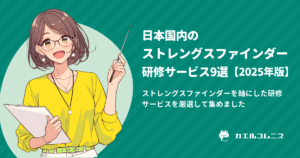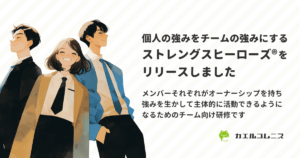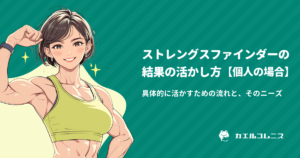はい、ごめんください。Gallup 認定ストレングスコーチのコスギです。
「ストレングスファインダー(クリフトンストレングス)を受けたら、コーチングしてもらうとイイらしい」とはいうものの……以下のようなギモンがあるのではないでしょうか。
- でも、コーチングを受けたことがないから、何がどうなるのかよくわからない
- 特に悩みも目的もないけど、お金を払ってまでコーチングを受けたほうがいいもの?
- そのうちコーチングを受けたいとは思っているけど、いつ受けたらいい?
- コーチングって、1回受ければいいのかな?
ということで、ストレングスファインダーを活かすコーチングを受けたいと思っている方や、迷っている方向けにまとめたので、参考になさってください。受けたいと思ったときが吉日ですよ。
結論:1回目は資質の理解、活かすのは2回目以降から
- 「才能」は誰にでもありますが、「強み」は育てて得られる能力です。
- ストレングスコーチングは、「才能(上位資質)」を「強み」に育てるための対話型のパートナーシップです。
- 特別な準備は不要です。最初は「資質の理解を深めたい」という理由でもOK。初めての方でもコーチと一緒に自分のペースで進められます。
- すぐに劇的な変化は起きませんが、月1〜2回を半年ほど続けると、自分の才能を活かした行動ができるようになり、迷いが減って決断しやすくなります。
- 料金はだいたい、60分で1万〜2万円くらいが相場です。継続セッションやグループコーチングは割安になることが多いです。
まずは単発セッションでコーチとの相性を確認してから、継続を検討するのがおすすめです。カエルコムニスでも無料でオリエンテーションをおこなっていますので、気になるコーチのオリエンテーションを受けてみるといいですよ。
\ 資質の特徴から紐解くのでわかりやすい /
そもそも、“コーチング” とは?
最近では少しずつ浸透してきた言葉ですが、「そもそも、コーチングって何?」「なんか新興宗教っぽい」という方は少なくありません。
色々な説明がなされていますが、ここではコーチングの世界基準を定めている、一般社団法人国際コーチング連盟(ICF)のサイトから引用します。
ICFでは、「コーチングとは、思考を刺激し続ける創造的なプロセスを通して、クライアントが自身の可能性を公私において最大化させるように、コーチとクライアントのパートナー関係を築くことである」、とコーチングを定義しています。
ICFはどのようにコーチングを定義付けていますか? – ICF Japan Chapter | 一般社団法人国際コーチング連盟 日本支部
……長いので、重要なキーワードを見ていきましょう。
「コーチ」「クライアント」という役割がある
コーチングは、雑談ともセミナーとも異なります。「コーチ」と「クライアント」に役割が分かれ、主に質問を中心とした対話になるため、最初は戸惑うかもしれません。
たとえば以下のように、コーチの質問に答えられない場合、自分が否定されたように感じる方も少なくありません。
コーチ「では今日、お話したいことは何ですか?」
クライアント「えっ……話したいこと……?」
(コーチングを受けてみたいと思っただけなんだけど……それじゃダメってこと??)
正直に「なんとなくです」と答えるだけいいのですが、初対面の相手ですから、「こんなことを言ったら変に思われるかも」と身構えていると難しいもんです。
特に、日本は上下関係のもとで 1対n の教育指導を受けてきた文化的背景もあり、質問には正しい答えがあるのが大前提。評価されることが当たり前なうえ、聴いてもらう経験が少ないため、対話に慣れていないですし。「話しあう」とは言うものの「聴きあう」とは言われませんよね。
ではコーチングは限られた一部の人のためかというと、そんなことはありません。コーチングを受けたいと思ったら、「コーチ」を選び、「クライアント」という役割を担うだけです。つまり、自分の可能性を広げていい。
コーチングは、クライアントのためのパートナーシップなんです。
コーチングはパートナー関係 = 対等な立場で契約を交わした相互協力の関係
日本で契約を交わしたパートナー関係というと、わかりやすいのが結婚ですね。(目的は人それぞれあるかもしれませんが)制度や法律が整備されているため、主には「今後の生活を継続しやすくなる」ことを期待できる関係です。
それから、仕事。結婚のように 1対1 ではないことのほうが多いので、パートナーという認識がしにくいかもしれませんが、契約関係として何を求められているのかは、結婚よりもわかりやすいです。たぶん。
コーチとクライアントは、プロフェッショナルなサービスに対価を支払う、ビジネスとしての契約関係です。友だちでも、家族でも、職場の上司でも、学校の先生でも、ましてや恋人でもありません。
だからこそ倫理規定があり、守秘義務があり、時間枠も決められています。こういった契約だからこそ、弱音や愚痴を吐いても、思考のクセに気づいて次の行動を選択できるようになるのです。安心して思考が自由になれば、人間は本能的に進むチカラを発揮します。
私はコーチとして、個人やチームのサードパートナーでありたい。
もし、愚痴が出てきたら?
コーチングは、傾聴と質問が主なアプローチになりますが、それだけの時間ではありません。
たとえば、クライアントが以下のように愚痴っぽくなったとき、あなたがコーチならどのように対応しますか?もしくは、どのように対応してほしいですか?

やっぱりね、ウチの上司ってホント馬鹿なんですよ。みんなそう思ってると思います。
A:みんなに馬鹿だと思われているんですね。それはイヤな上司ですね〜
B:馬鹿だと思っているんですね。それって、上司にも事情があるんじゃないですか?
C:みなさんがそう思ってる、と思うんですね。◯◯さんは、特にどんなときにそう思うのですか?
D:「みんな」って誰ですか?そう思っているのは、◯◯さんだけということはありませんか?
E:そんな会社、早く辞めたらいいんですよ。まあ、私の上司も大概でしてね……
コーチングは、C のアプローチをします。
ちなみに他の回答について(クリックで開きます)
A:同調するだけでなく、クライアントの言葉をネガティブに解釈してしまっています。
B:クライアントの話を聴いているようで聴いておらず、正論で対立する姿勢になっています。
D:言葉尻を捉えて揚げ足を取るように聞こえ、クライアントの安心感を損ねてしまいます。
E:相手の話を勝手に結論づけたうえ、自分語りを始めているので論外です。SNSのクソリプかな?
どれも、ICFの定めた倫理規定やコア・コンピテンシーの観点から見ると不適切です。とはいえ正解はなく、これがセッションの中で瞬間的に起きたことならコーチングが継続する可能性も十分あり、相互の信頼関係によるところは大きいです。
ここでのポイントは「上司が馬鹿かどうか」ではなく、「クライアントが何を問題と感じ、どんな意味づけをしているか」を探ること。話を聴いていくことで、以下のようなことに気づくかもしれません。
- 本当はチームで話し合って進めたいのに、上司の判断で進められてしまう
- 時間がないのは理解している、けれどこのまま進めたら失敗が目に見えている
- 後悔するような仕事をしたくない
これが「思考を刺激し続ける創造的なプロセス」です。
さらに、ここにストレングスファインダー(クリフトンストレングス)を使うなら、〈調和性〉や〈慎重さ〉に起因しているかもしれないのです。状況が見えてくると、何ができるかを自然に考えられるようになります。これがストレングスコーチングのおもしろさ。
コーチングは、考えや気持ちを整理する場であると同時に、新しい選択肢や行動の可能性が広がる時間です。解決するのはコーチではなく、クライアント自身。そのために、一緒に探求します。
だから、コーチングはパートナーシップなんです。
ストレングスコーチングと一般的なコーチングの違い
特定のツールを使ったり、特徴のあるアプローチをする場合「◯◯コーチング」と呼ぶことがあり、「ストレングスコーチング」は、ストレングスファインダー(クリフトンストレングス)を活用したコーチングのことです。
自己分析に役立つツールを使った場合と一般的なコーチングの違いとして、メリットとデメリットを挙げてみました。ツールはストレングスファインダーだけでなく、VIA ストレングス(VIA 診断)やビッグファイブ診断などでも同様ですね。
ツールを使うメリット
- 無意識のパターンが言語化されているため、行動原理を理解しやすく自己認識が早く進む
- 自分の特性に基づいた行動指針が明確になるため、次のアクションへの違和感が減り実行しやすい
- チームや組織で共通言語として活用でき、相互理解や補完関係が促進される
ツールを使うデメリット(リスク)
- ネガティブなパターンも同時に理解できるため、問題にフォーカスしがちになる
→ コーチングによって全体を俯瞰する - 問題解決に意識が向いてしまい、本来の目的を見失いがちになる
→ コーチングによって本来の目的に立ち返る - 診断結果を固定的な限界と誤解し、「このタイプだから無理」と可能性を狭めてしまう
→ コーチングによって背景に目を向け成長を促す
ツールを使わないメリット
- 外部の枠組みに縛られず、クライアント自身の言葉で自己を定義でき、より本質的な気づきに到達しやすい
- 「私は○○タイプだから」という固定観念が生まれにくく、成長や変化の可能性を常に開いておける
- セッションごとに新たな発見があり、自己探求のプロセス自体が深い学びと成長の機会になる
ツールを使わないデメリット(リスク)
- 白紙の状態から始めるため、自己理解の土台作りに多くのセッションを要する可能性がある
→ コーチングスキルで効率的な質問を促進 - 客観的な視点が入りにくく、自分では気づきにくいパターンや才能を見逃す可能性がある
→ コーチの観察力とフィードバックでカバー - 共通言語がないため、チームや組織での相互理解や協働が進みにくい
→ コーチが翻訳者として機能する
よく、ストレングスコーチングは結果の理解に重点が置かれるため、「強み」を出発点とすると思われがち(おそらくAIに聞いてもそのように答えます)ですが、これは大きな誤解です。コーチングをする限り、ニンゲンファーストであり、目的ありきです。
ストレングスコーチングも一般的なコーチングも、クライアントが望む未来に向かって伴走するという本質は同じです。ツールはあくまで「地図」のようなもの。目的地(ゴール)を決めるのはクライアント自身であり、コーチはその旅を共にするパートナーです。元々「コーチ(Coach)」は馬車、つまり「目的地へ人を運ぶもの」ですからね。
コーチングを受けても効果を得にくいケースは?
よく「ストレングスファインダーをやると自己肯定感が上がる」と言われますが、上がるものは下がりやすいです。強みを開発するためには自己受容や自己基盤、要するに “自己肯定感に振り回されない土台” を強化する時間がかかることが少なくありません。
他にも、以下のような状態では効果を実感できるまでに時間がかかることもあります。
自分と向き合う準備が整っていないとき
「なんとなくだけど、受ければ何とかなるかも?」と思う気持ちは自然です。自分のテーマをまだつかみきれていない段階では、言葉が出にくく迷いが大きいものです。
コーチは「今ここで話せること」から一緒に探り、少しずつ言語化していきます。テーマが明確になるプロセスそのもののなかで、自己認識を深めていきます。
振り返りや対話に慣れていないとき
自分の思考や感情を言葉にする習慣がないと、最初は「何を答えるのが正解なのか」「何を話せばいいのかわからない」と戸惑うことがあります。
まずは話したいことを話していただくと、パターンが見えてきます。頭に浮かんだことを口にしながら、聴いてもらう経験を重ねましょう。
「誰かに正解を教えてほしい」と思っているとき
自分の外に正解を求める傾向が強いと、自己認識に時間がかかります。また、自分の弱みにばかり目がつくようなら、自己受容が必要です。
そのままでも本人の人生ですが、コーチングによって自分自身の答えを見つけるチカラが育てば、迷っても迷い続けることなく進みやすくなります。
心身に明らかな不調をきたしているとき
コーチングでは診断や治療は行えないため、必要に応じて専門家につなぐことが最善の選択となります。
- カエルコムニスは、コーチが産業カウンセラーの資格を保持しているからこそ、原則、近くの医療機関に相談することをオススメしています。
コーチングはパートナーシップですから、答えを与えるものではありません。クライアント自身が素直に自分を見つめ、自己認識を深め、選択肢を広げて行動し、成果にコミットするチカラを育てることを前提とした契約関係です。
基本的には継続を想定することをオススメしますが、継続を前提に、まずは単発でコーチの雰囲気を知るのも良いのではないでしょうか。初回セッションは資質を読み解くものが多いので、継続する前に受けておいて損はないですからね。
ストレングスコーチングなら、1回受けるだけでもいい?
過去の私は、それでもいいと思っていました。
ストレングスコーチングは結果を読み解くコンサルティングに近いことが多く、上位資質の理解を通じて一気に自己認識が進み、万能感を得られます。普段からセルフマネジメント力が高い方は、上位資質が腑に落ちただけでも得られるものが大きいです。
しかし、理解や認識ができた程度では、良くも悪くも同じパターンを繰り返します。「わかっているけどできない」がニンゲンの常ですからね。
また、誰もが持っている「才能」は、毎回最高のパフォーマンスを発揮できる「強み」とは限りません。ストレングスファインダーの生みの親である、ドン・クリフトン博士は「強みの開発には、他者との関係が不可欠である」と明言しています。つまりコーチングを継続することは、自分の強みを開発し、育て続けることに他なりません。
ストレングスコーチングを継続するなら、どれくらいの期間がベスト?
では、どれくらい継続すればよいのでしょうか。
さまざまな研究結果から「回数や期間は必ずしもコーチングの効果を保証しない」に総括されます。要するにケース・バイ・ケースなので、コーチと相談しながら一緒に決めていくのがベストです。
- つまり「量より質」ということですが、さまざまな研究結果を調査すると、質を左右する要因は以下のものがあると考えられます(コスギの解釈が少し入っていますので引用は推奨しません)。
コーチングの質を左右する要因(クリックで開きます)
- コーチとクライアントの関係性(ワーキング・アライアンスの3要素)
- 目標合意(Goal agreement):両者が目指す方向に合意しているか
- 課題合意(Task agreement):その目標に向けた方法や課題に納得できているか
- 絆(Bond):信頼・安心感があるか
- 目標設定の明確さ(SMART)
- 具体的、測定可能、達成可能、関連性、明確な期限
- 経験学習サイクルの実施
- 具体的経験 → 省察的観察 → 抽象的概念化 → 能動的実験 → ……
- 環境や協力者のサポート
- 職場や家庭環境、上司、同僚、家族の協力があると効果的
- クライアントの意欲
- 「すでに変化への意欲がある人」の方が、短期でも効果を得やすい
- 自己効力感
- 「できる」という実感の積み重ねが学習と行動の成果をつなぎやすい
- 構造化された介入
- セッションの質的構造(振り返り・課題・次回の合意)や課題の実践がある方が成果が高まりやすい
経営層を対象とした「エグゼクティブ・コーチング」といわれるものはクライアントに上記のことを求める分、効果も最大化されます。ですが一般的には「そもそも目標設定が苦手なんだけど……」「自信がなくて迷う……」と、上記の項目を埋める感じになることのほうが多いでしょう。
目的や本人の状態にもよりますが、最低3ヶ月、6ヶ月以上/10回以上のセッション+実践が目安になります。
とはいえ、単発でさまざまなコーチに相談する方もいれば、1年に2回振り返りの機会を設ける方、20年以上毎月同じコーチで続けている方もいるため、一概には言えません。それに、クライアント力がついてくると自らコーチングの質を上げられるので、たった10分のコーチングでも行動が促進されるようになります。
ちなみに Gallup は、マネージャーがスタッフと毎週15〜30分間、有意義な会話をする習慣の重要性を語っています。職場におけるストレングスコーチングの形は、これが理想ですね。だから Gallup は社内コーチの育成を進めており、ストレングスコーチの資格はそのためのものでもあります。
初めてストレングスコーチングを受ける方へ
弊社カエルコムニスには、「コーチングは初めてなんです」と仰る方が9割以上です。
よくわからないけどストレングスファインダーをやってみた → 診断結果にビックリして活用方法を調べる → コーチングというものが必要らしい!という流れで、ストレングスコーチングを知ることが多いようです。実際、私がコーチングを知ったのもこの流れでした。
コーチングを実施する時間を「セッション」と呼びます。30〜60分が一般的で、この間にずっと話してもらうということはなく、コーチと対話しながら進めます。「あっという間だった!」という感想を持つ方が多いです。
コーチングを初めて受ける方は、なにか準備しておいたほうが良いのではと思うことがあるかもしれませんが、「これが必要!」「これを準備しておくのが当然!」というものは特にありません。
だいたい、以下のような流れで進むことが多いです。
- 話したいことの意図や得たいものはなにか(ゴールの確認)
- これまではどんなことができていたのか(リソースの認識)
- それはどの上位資質を使えていたからなのか(才能の認識)
- セッションを振り返って、どんなことを得られたか(ゴールの振り返り)
- いつまでにどんなことをしたいか(アクションの検討)
とはいえ、コーチングはナマモノですから、このとおりにならないことも少なくありません。
あえて心の準備をしておくとしたら、「すぐに効果を得られるものではないんだ」「主導権は自分にあるんだ」「コーチを困らせても大丈夫なんだ」と認識しておくことくらいでしょうか。
まとめ:コーチングは受けるべきか否か
そもそもコーチングは魔法のように即座に効果を得られるものではなく、長期的なパートナーシップにより自分の可能性を最大化するものですから、1回受けた程度で判断できるものではありません。ですから、コーチングを受けてみたいと思ったら、受けてイイんです。直感が大事。
コーチの選び方
コーチングは国家資格ではないために、どんなコーチを選んだら良いのか迷うこともあるでしょう。迷ったら「自らもコーチをつけているコーチ」もしくは「ICFの資格を保持しているコーチ(ACC・PCC・MCC)」を選ぶのがオススメです。つまり、自己研鑽しているコーチです。
ICFの資格は、そのプロセスでメンターコーチング(プロのコーチからのトレーニング)を受けています。そして、倫理規定とコア・コンピテンシーを学んでいますので、コーチングの質に対する理解が深いこともポイント。
それ以外にも、コーチングにはさまざまな流派があるので、以下のようにコーチのアプローチも千差万別です。これはセッションを受けてみると判断しやすいですね。
- 図を用いて理論的に説明するコーチ(コンサルティング的アプローチが多い)
- 時間をかけてじっくり話を聴くコーチ(カウンセリング的アプローチが多い)
- 特定のスキルの向上を目標とするコーチ(ティーチング的アプローチが多い)
- 感情にフォーカスするコーチ(セラピー的アプローチが多い)
- 複数人のグループを対象にするコーチ(ファシリテーション的アプローチが多い)
- クライアントの自主性による流れを重視するコーチ
- クライアントの思考や感情を揺さぶるコーチ ……など
最後のは何だ?って思うかもしれませんが、クライアントとして成熟してくると、こういった熟練のコーチが必要になることもあります。
良いコーチはクライアントの自走を促すので、1対1 のコーチングの最中でも、コーチが気にならなくなるほど存在感が薄くなります。そうなると、もうコーチングは不要かなと思うことがあるかもしれません。実際、短期間で終わるコーチほど単価が高い場合が多いです。
まずは、資質理解の先にある何かを活かすために、ストレングスコーチングを受けてみませんか?
\ 資質の特徴から紐解くのでわかりやすい /
AI(ChatGPT)のコーチング BOT をつくりました
まだ心の準備が整っていないということでしたら、こちらの ChatGPT でつくったコーチング BOT をお試しください。ストレングスファインダーは使用しませんが、国際コーチング連盟(ICF)が公開した AI コーチングの基準に基づいてつくったものです。
とはいえ、AI なので時々不自然な質問をしてきますし、あえて人間味を抑えていますが、コーチングを受ける練習としてわからないことを「わからない」と伝えたり、変化球の質問に答えたりするトレーニングにもなります。
気になる点がありましたら、SNSやお問い合わせフォームよりご相談ください。