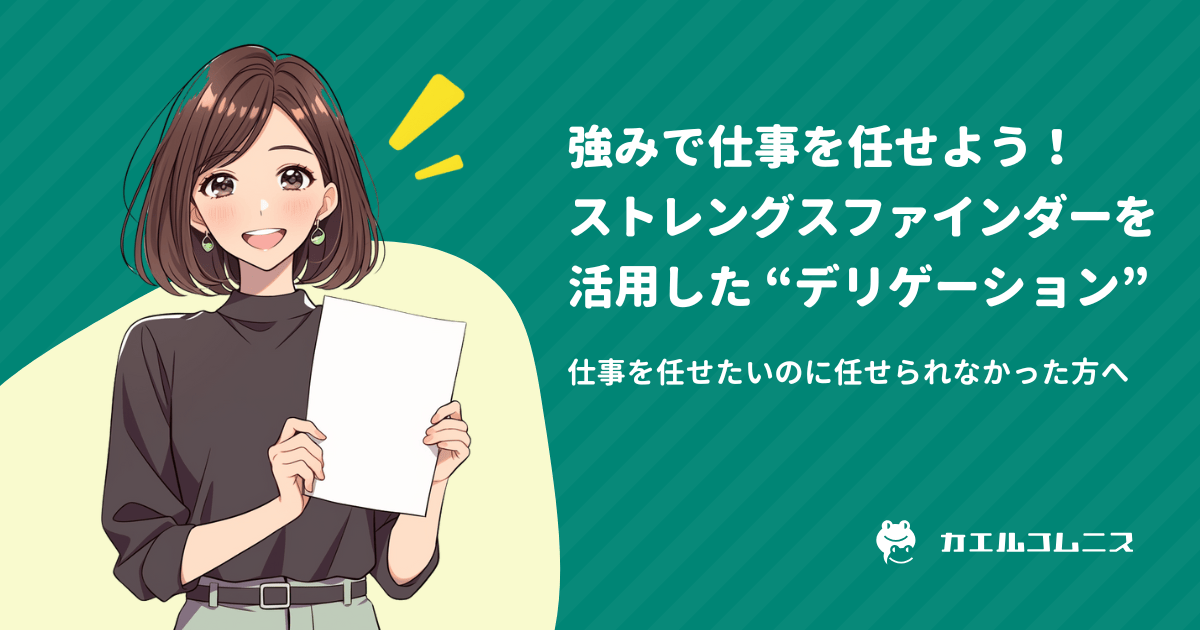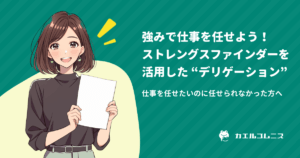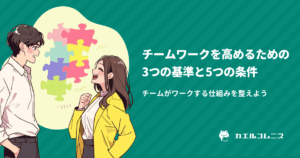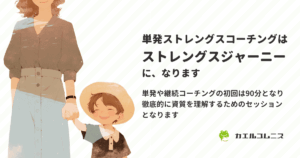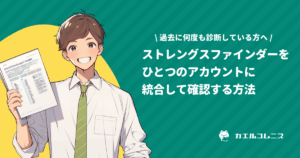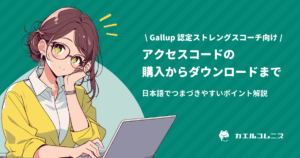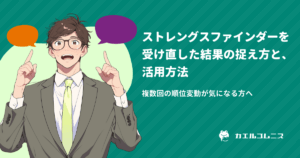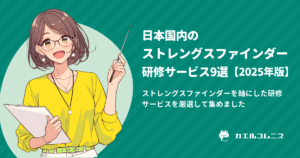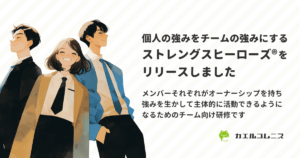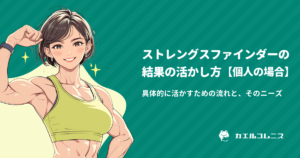はい、ごめんください。Gallup 認定ストレングスコーチのコスギです。
今回のテーマは「仕事を任せる」ために、ストレングスファインダー®(クリフトンストレングス®)を活用するためのヒントをお伝えします。
「あ〜、説明するより自分でやったほうが早いかも……」
「結局、任せたところでやり直しちゃうしなあ……」
「失敗されたら、結局、責任取るの自分だしな……」
「「「いや、任せるべきなのはわかってるんだけど……!」」」
そんな方でも、「デリゲーション(Delegation)」のメソッドをなぞってみると任せやすくなりますよ、という記事です。もしかしたら「確かに、任せられているときは似たようなことをしていたかも!」と気づけるかもしれません。
仕事を任せられない3つのパターン
仕事を任せることの大切さは、きっと多くの方が理解しているはずです。頭では。
でもこれが、なかなかうまくいかないのが現実……
任せたほうがいいと思いながらも、自分で手を動かしてしまう。任せてみても、逐一チェックをしないと気が済まない。任せたものが期待どおりの質になっておらず、結局自分が手直しする……まあ、あるあるですよね。それぞれ具体的に見ていきましょう。
時間がないから、自分でやったほうが早い
説明する時間がもったいない。今すぐ終わらせたいんだよ……!
何をどう伝えたらいいかを考える余裕すらないときは、「人に頼む」というプロセス自体が負担に感じてしまいます。
この背景には、脳の節約モードともいえる「認知の省エネ」が働いています。考えるよりも、手を動かす方がラクと感じる状態。だから、目の前のタスクを自分で引き取ってしまう。コレを繰り返していると、目の前のタスクに追われて重要なタスクがどんどん遅れることになりかねないんですよね。
これは〈活発性〉、〈達成欲〉、〈目標志向〉、〈適応性〉など、行動したい才能の傾向としてみられるかもしれません。また、戦略的思考力が高いと「自分が理解して納得してから説明しなければ」と必要以上に感じやすく、結果「メンドクサイな……」と思うかもしれません。私は〈活発性〉が高いので、説明しながら手を動かせば終わるやんと感じたら、全部自分でやっちゃいます……😇
ちゃんとやってくれるか、不安で任せられない
結局、やり直すことになったら意味ないし……
苦手なことはともかく、成果物に対して完璧主義の傾向があると「自分の方が早くて正しい」と思い込みやすいです。
この背景には、「高い水準を求める」「誤りを確実になくす」の2つがあり、後者の傾向が強いほど他者に任せることへの抵抗が強いとされています。相手への信用はもちろんですが、手順を可視化せず丸投げすれば、当然「品質が担保できない」と不安になるのも当然です。
コレを繰り返していると「◎◎さんは自分でやらないと納得しないから」と認識され、周囲も手出しできなくなってしまいかねません。結果、孤立するうえに終わらないという負のスパイラルに。
これは影響力系だけでなく、〈回復志向〉、〈責任感〉、〈慎重さ〉など、物事にしっかり向き合いたい才能の傾向としてみられるかもしれません。私は〈最上志向〉が高く〈内省〉もあるため、考えているうちに求めるレベルがどんどん上がっていく自覚があります……😇(ついでに〈戦略性〉も高いのでゴールが移動するオマケつき)
失敗したら、怒られるのが怖い
もしミスされたら、怒られるのは自分なんだよな……
心理的に余裕がないときや、失敗が許されにくい職場環境では、「人に任せるくらいなら、自分が責任を持ってやった方が安心」と感じやすいです。
現場から上がったばかりの中間管理職に多く、よくわからないマネジメント業務と同時に、これまで以上の成果を求められる板挟みの立場で葛藤してしまうのも無理はありません。チームの育成よりも、売上を確保しなければならないというプレッシャーがあれば、なおさらですよね。
このような場合「人は得より損を約2倍強く感じる」という損失回避バイアスによって、メンバーに任せて損するリスクより、自分が一定の得を確保して、残りをメンバーで補うことで乗り越えようとすることがあります。これが続くと、いつまでたっても重要な仕事を任せることができません。これは、メンバーの自己効力感にも影響します。
これは立場や状況など外部要因の影響が大きいですが、特に人間関係構築力の高い方は「自分が火種になることは避けなければ」と思って抱え込みやすいかもしれません。切ないですね。
資質を活かして任せるための “ストレングス・デリゲーション”
「デリゲーション(Delegation)」という言葉は馴染みがないかもしれません。直訳すると「権限を譲渡する」「委任する」といった意味で、ざっくりいうと 「人に仕事をうまく任せる技術」 のことです。
この「デリゲーション」に、中心的な理論はありません。これまでに、学者や専門家が「どうしたらうまく任せられるか?」を、リーダーシップ、チームの信頼関係、仕事の動機づけ……など、さまざまな角度から研究したところ、3つの重要な要素が共通しているのではないかと言われるようになりました。この要素については、さまざまな解説があります。まるで、現場の知恵袋みたいですね。みんな苦労してるんだな……
カエルコムニスでは、任せることへの苦手意識を克服するのではなく、相手の上位資質を刺激して受け取ってもらいやすくするという考え方で、コーチングアプローチ × ストレングスファインダーの結果を活かして進める流れをまとめました。
デリゲーションに必要な3つの要素
そもそも「デリゲーション」は、単に自分の負担を減らしたり、仕事を分散させるだけのものではありません。仕事を委任することで相手の成長を促し、チームや組織全体の成果に貢献することを意図するものです。そのために依頼者側に必要な要素は、以下の3つ。
- 成果と目的が双方で合意されていること(ゴールの共有)
- 判断範囲と資源が明示されていること(自律性の設計)
- プロセスや結果を振り返る仕組みがあること(学習の仕組み)
デリゲーションに必要な要素をもう少し詳しく(クリックで開きます)
①成果と目的が双方で合意されていること(ゴールの共有)
仕事を任せるうえで、まず最初に必要なのは「何をやってもらいたいのか」を、具体的な共通認識によって定めることです。これは必要性を疑う余地もありません。
すべての人間には価値観や世界観があり、認識はズレるのが大前提です。だからこそ、少なくともゴールの認識を明確に合わせておくことは重要です。この大前提、忘れがちなんですけども。ここがあいまいなままスタートすると、「任せたつもりだったけど、思ってたんと違う」「何をゴールとしていたか、あとで揉める」といったトラブルになりがちです。
また、「なぜそれをやるのか」という目的を伝えることで、タスクが「単なる作業」から「意味のある仕事」に変わります。人は、納得していないことには本気になりにくいものですからね。これによって、その後の自律的な行動や、結果の評価・学習の効果が変わります。
②判断範囲と資源が明示されていること(自律性の設計)
任された側がスムーズに動けるかどうかは、「自由にやっていいよ」と言われたかどうかではなく、「どこまでなら自分で判断してよいか」が明確になっているかどうかに左右されます。
たとえば、予算、相談すべきタイミング、ツールや協力者、これまでの資料、そしてNG項目も把握しているかどうかで動き方が変わります。これらがあいまいなままだと、任された側は判断に迷って過剰に確認したり、逆に自分勝手に行動したりしてしまいますよね。
成果物や目的が明確でも、「ネットにある画像を拾って、AIにつくってもらいました!」みたいなことが起きやすい昨今ですから、依頼者は「判断と行動の枠」を設計しておくことが重要。
これまで自分で仕事を引き受けてきた方の中には「ここまでしてあげなきゃならないのか……」と、率直にメンドクサイと感じる方も少なくないかもしれません。デリゲーションの目的は負荷分散だけではないため、任せることに意義を感じているのなら、挑戦してみてはいかがでしょうか。
③プロセスや結果を振り返る仕組みがあること(学習の仕組み)
ここでいう「学習」とは、知識のインプットや勉強のことではなく、経験を振り返って糧とする成長のプロセスを指します。具体的には、任せている最中に振り返って調整したり、終わったあとに振り返って次に活かしたりするものです。
こういったフィードバックの仕組みがあることでスムーズに進むのはもちろん、任せた相手に「ちゃんと見てもらえた」という実感が生まれ、次回以降の信頼感や責任感にもつながります。逆に、フィードバックがなければ、成功も失敗も放置され、学習が組織に残りません。
個人ではなくチームや組織として仕事をする以上、今後も仲間としてやっていきたいのなら、重要な仕組みですよね。
では、それぞれのステップで重要なポイントを押さえ、コーチングアプローチで進めてみましょう。指示することに苦手意識のある方でも使える方法です。やり方が違うだけなので、押してダメなら引いてみましょ。
一緒にゴールを描く
仕事を任せるとき、まずやるべきことは「何をどこまでやるのか」をはっきりさせること。それを一方的に伝えるのではなく、一緒に言語化することがポイントです。
- 成果物(アウトプット)
何をどんな形で期待するのか、具体的な完成図。What です。 - 目的・価値
何のためにこの仕事があるのか、誰のためのものなのかという意味。Why。 - 期限・マイルストーン
期日だけでなく、進捗共有するタイミングも。When ですね。
「成果物はアウトプットではなく、アウトカムであるべきは?」と思った方もいるかもしれません。アウトカムは、成果物(アウトプット)によって生まれた結果や影響を指すため、What = アウトプット、What × Why = アウトカム と考えてみるとわかりやすいです。
相手の経験が浅く新しい仕事ならアウトプットを重視し、相手がベテランで信頼関係も厚いならアウトカムを重視すると、相手の能力に合わせた適切なゴール設定になりますよ。なお、5W2H だけでなく、SMART のフレームワークで目標の妥当性を検証しておくと、納得感のある目標として説明しやすくなります。
任せる相手のストレングスファインダーの傾向
- 実行力
-
ゴール設定の明快さと才能の発揮が比例します。目的が手段になっていると混乱しやすいので、成果物の認識を合わせておくことが大切です。
- 影響力
-
アウトカムと合わせ、「この仕事をあなたに任せる理由」が明確だと動きやすいです。
- 人間関係構築力
-
「この仕事がどんな人に役立つのか」が明確だと動きやすいです。
- 戦略的思考力
-
ここでは「ゲームの勝利条件」「ゲームの時間軸」の認識を言語化してもらうに留め、自律性の設計に進みましょう。
ゴールを合わせるための問いかけの例
任せる側はコーチではないので、探究的な問いかけだけでは仕事が進みません。限られた時間内で共通認識をつくるために、クローズ(確認)→ オープン(共有)の例を挙げておきますので、状況に応じて使い分けてください。
- わからないことがわからない、と思う点はありますか?(盲点の確認)
- いつまでに何をどうすればいいか、あなたの認識を教えてください(認識の確認)
- この仕事が終わったとき、どんな状態になっていると思いますか?(ゴールの認識共有)
- どんなふうに進めると、お互いに気持ちよく終えられそうだと思いますか?(進め方のポイント共有)
- この仕事は、誰にどんな価値を生むものだと思いますか?(重要視する目的の共有)
大切なのは、相手の返答が「わかりました」ではなく「〜ということだと思っています」と、具体的に答えてもらうこと。
これにより、一方的な指示ではなく、ゴールの認識を解像度高くすり合わせることで、向かう先がブレにくくなります。また、お互いに「ただのタスク」ではなく「意味のある仕事」として扱うようになるため、最終ステップの学習を促進しやすくなります。
なお、「わからないことがわからない」という状態で「質問はありますか?」と尋ねられても答えられません。そのため、最初の確認事項にしています。もしわからないことだらけでも、どこまでわかっているのかを話してもらうことが大切です。そこからすり合わせていきましょう。
資質が違うのはもちろん、自分とは違う存在なのだから、すぐに同じ認識になれる人なんていません。だからこそ、ゴールくらいは共にしておきたいのですよね。
相手が自律的に動きやすい境界線を設計する
ゴールを共有したら、次は「どう動くか」を安心して任せるための枠組みづくりです。ここで大切なのは、「好きなようにやってね!」ではなく、安心して思い切り動ける枠( How のための境界線)を明確にすること。境界線が合意できれば相手は遠慮なく判断して行動でき、依頼する側も安心して任せられます。
- 判断の範囲を明示する
何をどこまで任せるのか、数字や条件で判断基準を明文化します。 - 利用できるリソースを共有する
使える時間、人、情報、ツールを事前にリストアップし、不足するものは誰がどのように行うかを決めておきます。 - 相談や報告のタイミングを決める
どのタイミングで何を報告するのか、中間共有の時期と連絡手段をあらかじめ取り決めておきます。
重要なのは、相手が自信を持って判断・行動できるように、あらかじめ「裁量の範囲」と「サポートの仕方」を定めておくことです。やり方は相手次第だからこそ、ストレングスファインダーとの相性が良いのですよ……!
任せる相手のストレングスファインダーの傾向
- 実行力
-
すでに How があるなら、出し惜しみせず共有しましょう。迷わず進んでくれますし、つまずくようなら一緒に How をアップデートして蓄積できる機会です。もし How が整備されていない場合は、ゴールに戻ってマイルストーンを調整しましょう。
- 影響力
-
良くも悪くも主体性が高く、リスクよりも経験を重視しやすいため、先に NG となる境界線を明確に合意しておきましょう。Why と合わせて納得できれば、限られた範囲で最善を尽くしてくれます。経験を積むことで、リーダーとして育っていきます。
- 人間関係構築力
-
サポートの有無でパフォーマンスが変わります。定期的に方向性と進捗を確認できるミーティングがあると安心して進めるため、その際の議題作成も任せ、時間の裁量を持ってもらいましょう。関わりを大切にすることで、チームとしての結束力を高めてくれます。
- 戦略的思考力
-
ここで「ゲームに利用できるリソース」が確定するため、戦略の見通しが立ちます。この時点で、成果物・期限・プロセス・裁量範囲・求めるサポートなどの言語化を促し、合意を得て進めましょう。相手の脳内に留めないことがポイントです。
自律性を設計するための問いかけの例
以下のような質問で、「どこまでを相手が判断できるか」「どこで支援が必要か」を具体的にしましょう。大切なのは、「わかりました」と答えてもらうことではなく、「私はここまで進めます」「ここは相談します」「進めながら相談します」と、具体的に宣言してもらうことです。ここが指示とは違うのですよね。
- 今の時点で、足りないと感じるものは何ですか?(準備のための棚卸し)
- 途中で状況を共有するとしたら、いつ・どんな手段がよさそうですか?(共有のルール化)
- どこまでの判断を自分で進められそうですか? 逆に、どこは確認したいと感じますか?(判断の線引き)
- 「この条件が決まっていれば進めやすい」と感じるポイントはなんですか?(行動の条件づけ)
- 緊急時や判断に迷ったときは、どのように助けを求めたいですか?(支援の設計)
これによってお互いの期待と行動範囲がはっきりし、不安や遠慮が減り、相手は自信を持って行動できるようになります。
曖昧なまま任せてしまうと、任せる側は不安で口を出したくなり、任された側は遠慮して動けなくなります。しかし「判断できる範囲」「使ってよい資源」「共有のタイミング」が合意できていれば、相手は主体的に動き、依頼する側も支援に集中できます。
相手に任せるための準備は、言葉とルールで「境界線」を一緒に設計すること。これができれば、任せることそのもののハードルは下がりやすくなります。
振り返りと調整で、次につなげる
仕事を任せたら、終わるまで丸投げではなく、進めている途中で確認や調整も大切です。うまくいっていることを見つけたり、詰まりそうなところを早めに整えたりすることで、任された人は安心して動けるようになりますからね。
振り返りやフィードバックは、アラ探しではありません。むしろ、うまくいったことを増やし、スムーズに進む工夫を見つけていく場として考えるといいでしょう。
- 進捗の確認と調整
事前に決めたタイミングで進捗を確認し、「ここまでは順調」「ここが詰まっている」といったポイントを一緒に整理します。 - 結果とプロセスの振り返り
成果物の評価だけでなく、完了までのプロセスを振り返り、達成できた点・好影響を生んだ工夫・舵を切り直した決断などを共有します。 - 次回へのアクション
振り返って終わりではなく、「次はこうしてみよう」を仕組みに取り入れます。
進捗確認の際、うまく進んでいるなら良いのですが、たいていの場合は何らかの問題が起きています。ここで「なぜこの問題が起きたか」と原因を分析したくなりますが、「じゃあどうするか」と調整して進めることを意識しておきましょう。人間の脳は批判的思考をしやすいので、ゴールに向かって進めよう、次に活かそうという意思を持つことが大切です。
また、学びを「気づいた人」だけにとどまらせず、「プロセスを回すための仕組み」に反映させることが重要です。正直、意思を持ち続けるのは疲れるんですよ。
「こまめにミーティングできたのが良かった」のなら、「困ったときにミーティングを依頼する」より「第2・4の金曜13時から最長30分間、1on1の予定を最初に入れておく」としたほうが、安心して動ける方が多いです。できない場合も含め、合意しながら決められるといいですね。
任せる相手のストレングスファインダーの傾向
- 実行力
-
基本的にはゴールをキッチリ満たすことに注力するため、効率性を求める傾向にあります。サイクルを回すほど効率化しやすくなるため、プロセスを調整していきましょう。
- 影響力
-
感情よりも事実に基づくフィードバックがあると、「それならこれがイイと思う」と自ら改善案を見つけて加速します。うまくハマると、想定以上の成果物を得ることができます。
- 人間関係構築力
-
「仕事の先に喜ぶ人の笑顔」「苦労も喜びも分かち合っている」の2つを実感できると、感情的な側面での改善案が出やすくなります。何度もゴールを確認して進めましょう。
- 戦略的思考力
-
抽象と具体を行き来しながら物事を見ているので、現在地とゴールの認識を言語化しながら納得感をつくっていくと、自ら黙々と行動していきます。
学びを引き出す問いかけの例
事実 → ポジティブな要因 → 改善アイデアの順で問いかけると、建設的な対話になります。
- 現在の進捗で、順調に進んでいる点はどこですか? → 何が良かったですか?(順調要因の確認)
- ここをもう少し整えると、スムーズになりそうな点はどこですか?(調整ポイントの発見)
- このタイミングでサポートがあると助かることはなんですか?(障害の除去)
- 完了してみて、「特に効果的だった工夫」は何でしたか?(好影響の整理)
- 次に同様の仕事をするとしたら、取り入れておきたいことは?(仕組みの改善)
また、コーチングの「スケーリング」という手法も使えます。
- 現在の進捗は、10点満点で何点ですか?(0点〜10点で回答をもらう)
- その点数にしたのはどうしてですか?(本人の認識を言語化)
- その点数にまで到達できたのは、何があったためですか?(進めたことを言語化)
- 何があれば、あと1点上がりますか?(次に進むためのアクションを言語化)
- そのために、私にサポートしてほしいことはなんですか?(支援の依頼を言語化)
このステップの目的は、「できた/できなかった」の評価を下すことではありません。「何がよかったのか」「どうすればもっと良くなりそうか」を一緒に考えることです。振り返りで見つけた学びを次のサイクルの起点にしていくことで、「任せて終わり」ではなく「任せて一緒に成長する」サイクルにしていきましょう。
このステップを習慣にしていくと経験学習のサイクルが回り、任せるたびにチームの動きが軽く、なめらかになっていきます。デリゲーションの本質は、チームを育てることなのかもしれませんね。
任せるのが得意な資質もある?
「ここまでしなきゃならないのか……」と正直ウンザリしている方、「ああ、これならできそうだな」と可能性を感じている方、そして「ここまでしないと任せられないの?」と疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。
以下に挙げたようなストレングスファインダーの資質は、任せることが当たり前の感覚を持っている傾向があります。ただし、資質が成熟すれば、すべての資質で任せることはできます(資質に優劣はありません)し、任せることが得意でも、デリゲーションできているとは限らないことに注意が必要です。なぜなら資質は単独で発揮されるものではないうえ、ご本人の経験や環境などの外部要因もあるためです。
- 〈アレンジ〉
-
「自分より得意な人がやったほうが効率的」と考えているため、自分が依頼されたことでも得意な人に依頼することがあります。さらに〈個別化〉が加わると、当然のように適材適所の感覚を持っていますので、マネージャーのような動きをしやすいです。裁量権があるとイキイキします。
- 〈指令性〉
-
手が空いていそうな人に直球で依頼します。「委任する」というよりは「指示する」に近く、「これやって」と有無を言わせないか、「これできる?」と YES か NO での返答を前提にする傾向があります。〈個別化〉が加わると、相手の能力に応じて指示を変える傾向があり、自然にリーダーとして動きます。
- 〈包含〉
-
「一緒にやろう」と自然に声をかけ、タスクを分担することにあまり抵抗がありません。まだ馴染んでいないメンバーや関わりが薄い人にも仕事を任せようとするのは、関わりが居場所をつくるから、という感覚が強いです。グループ全体の関与度を高める役割を果たしてくれる存在です。
- 〈公平性〉
-
仕事量の偏りにアンテナが立ちやすいため、誰かにタスクが集中するよりも、可能な限り分担することを良しとします。また、手順やルールを明確にすることで、誰でも同じ基準で成果物を得られるように整えることを好みます。「誰かに任せる」というより「担当を分ける」という感覚ですね。
- 〈成長促進〉
-
人の成長を喜びとするため、任せることを「育てる機会」として捉える傾向があります。「やったことがないなら、ちょうどいい機会かも」と考え、丁寧にタスクを渡します。途中経過でもこまめに声をかけ、小さな進捗を拾い上げて励まします。
ちょいちょい出てくる〈個別化〉は、単独では「(相手に合わせて)仕事を引き受ける」傾向が強いですが、任せることが当たり前な資質と組み合わさると「(相手に合わせて)仕事を任せる」傾向が生まれます。
逆に、これらの資質が上位にある方は、今まで無意識に任せていたことを、「デリゲーション」というスキルに昇華することで圧倒的な強みになりやすいとも言えます。
たとえば〈アレンジ〉は効率性を重視する分、学習に対する興味は薄いですし、〈成長促進〉は学習による成長を重視しますが、ゴール設定への興味は薄いです。デリゲーションのプロセスを上位資質で補うことができたら……めちゃくちゃワクワクしますね!
とは言っても、任せられない……と思ったら
ここまで読んで、「任せるって、こういうふうに考えたらいいのかもしれない」「デリゲーションという枠組みを使えば、自分にもできそう」と思えたら、ぜひ仕事に活かしてください。やり方は色々ありますが、大切なのは以下の3つです。
- 成果と目的が双方で合意されていること(ゴールの共有)
- 判断範囲と資源が明示されていること(自律性の設計)
- プロセスや結果を振り返る仕組みがあること(学習の仕組み)
まずはゴール設定が一番のキモ。手段が目的化しやすかったり、目標が曖昧になりやすい方は、以下の GPT を使ってみてください。ChatGPT が目標を評価して、調整のためのアドバイスをしてくれます。
ChatGPT を使い慣れている方なら、この記事のURLを参照させて「この記事を参考に、私が今抱えている仕事をデリゲーションするための相談に乗ってください」と依頼するのもアリよりのアリです。特に、戦略的思考力が高い方は考えてから動くので、先に AI と壁打ちしておくほうが見通しが立ちやすいのですよね。
とはいえ、「理屈はわかったけれど、それができたら苦労しない……!」と感じられる方も少なくないですよね。重要性を理解しているからこそ、葛藤しているわけですし。
「やっぱり、自分には難しいかもしれない」
「頭ではわかっていても、いざ任せようとすると不安になる」
「自分の強みを、どう活かせばいいのかわからない」
こういった悩みや不安に、一人で向き合うのは難しいこともあります。ストレングスファインダーを扱うコーチと一緒なら、あなたの上位資質の持つ意味を丁寧に紐解きながら、今の状況と理想の状態との間にあるギャップを少しずつ埋めていくことができます。
無理に変わろうとしなくても大丈夫。抱えている悩みを分かち合い、俯瞰するところからやってみませんか?
\ 資質の特徴から紐解くのでわかりやすい /